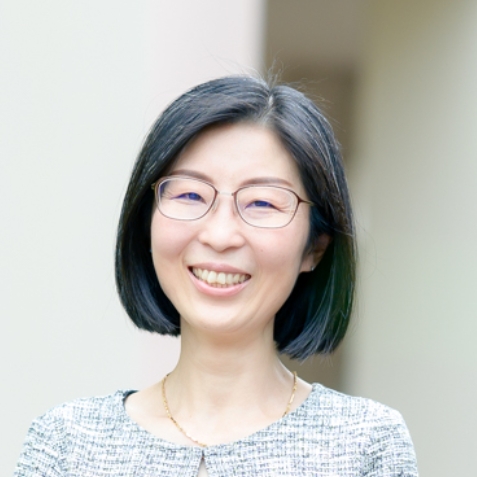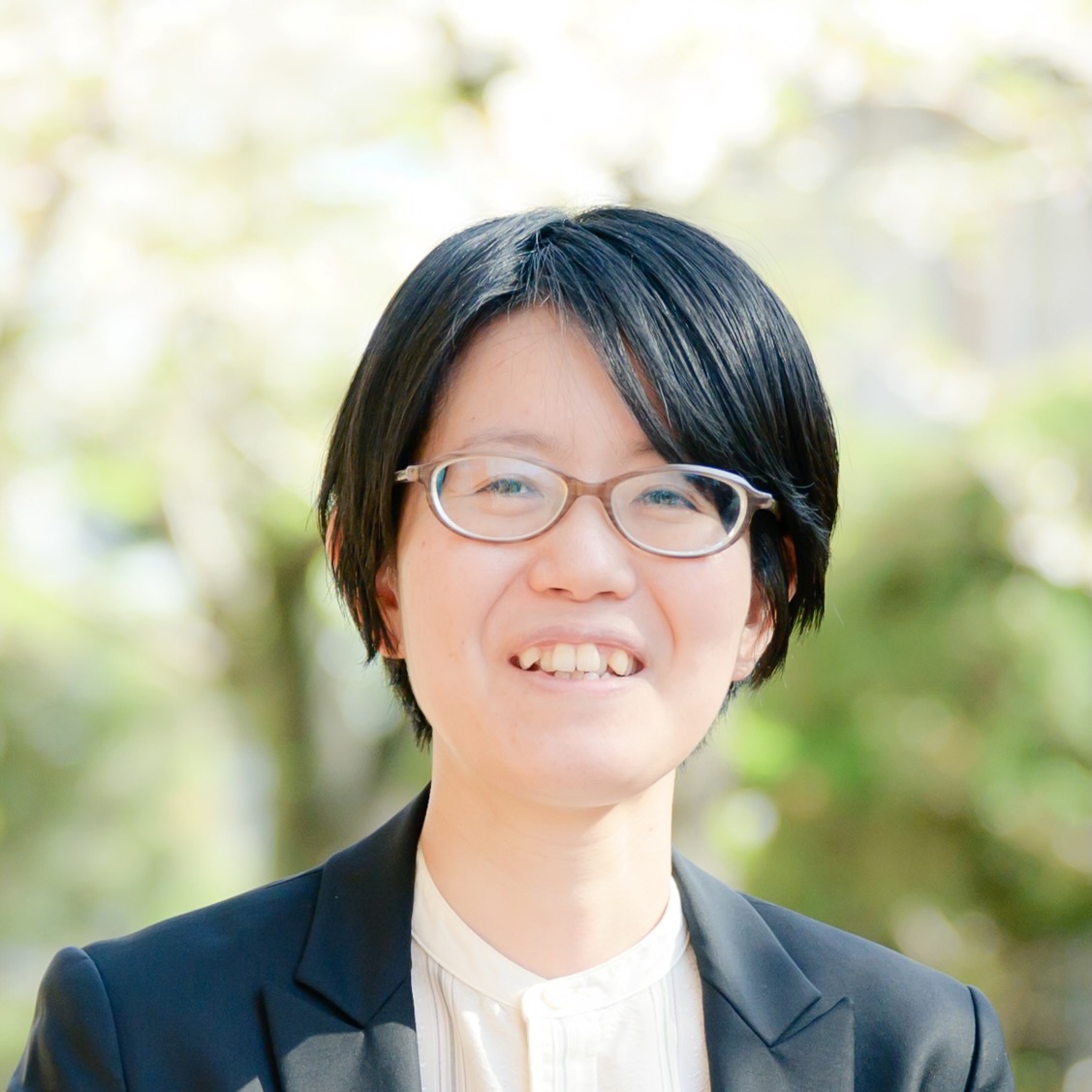PROFILE
岩井 真澄IWAI MASUMI
詳細をみる
国立音楽大学音楽教育学科幼児教育専攻を卒業後、都内の私立幼稚園にて担任、主任として勤務。
その後東京家政大学大学院人間生活学総合研究科児童学児童教育学専攻修士課程を修了。
立教女学院短期大学非常勤講師、東京未来大学特任講師、大妻女子大学助教を経て現職。
専門:
幼児教育
主な担当科目:
保育内容総論(保育指導法)/保育カリキュラム論(計画と評価)/教育実習Ⅱ(幼)など
-
保育・教育に興味をもった理由
集団登校のリーダー。
子どもたちの喜ぶ姿が嬉しかった。

 小学6年生の時、集団登校で小学1〜2年生の小さい子どもたちを連れて歩いていたんです。せっかくだから楽しくしたいと即興で作り話をしながら歩くんですが、子どもたちがキラキラした目で聞いてくれるんです。「ねえねえ、明日も聞きたい!」なんて言ってくれる。こんなに喜んでくれるんだと嬉しくなった。それから毎日お話をするように。これが子どもと関わる楽しさに気づいた原体験。それと、小学1年から高校2年の11年間、NHK の児童合唱団に入っていました。歌うことって楽しい。みんなと心を合わせることも楽しい。音楽を通して、いろんな人や世界とふれあうことができた。音楽の道に進むつもりはなかったのですが、好きなことを選んだ結果、音大附属の高校へ。大学は音大の幼児教育専攻に進み、音楽に囲まれた環境の中で幼児教育を学びました。今振り返るとなんて豊かな時間だったんだろうと思います。余談ですが、音大ならピアノが上手なんでしょ?と言われることが多いですが、実はピアノは一番の苦手。今、ピアノが苦手な学生の気持ちがすごくよくわかるので、あの時に苦戦してよかったな、とポジティブに捉えています(笑)。
小学6年生の時、集団登校で小学1〜2年生の小さい子どもたちを連れて歩いていたんです。せっかくだから楽しくしたいと即興で作り話をしながら歩くんですが、子どもたちがキラキラした目で聞いてくれるんです。「ねえねえ、明日も聞きたい!」なんて言ってくれる。こんなに喜んでくれるんだと嬉しくなった。それから毎日お話をするように。これが子どもと関わる楽しさに気づいた原体験。それと、小学1年から高校2年の11年間、NHK の児童合唱団に入っていました。歌うことって楽しい。みんなと心を合わせることも楽しい。音楽を通して、いろんな人や世界とふれあうことができた。音楽の道に進むつもりはなかったのですが、好きなことを選んだ結果、音大附属の高校へ。大学は音大の幼児教育専攻に進み、音楽に囲まれた環境の中で幼児教育を学びました。今振り返るとなんて豊かな時間だったんだろうと思います。余談ですが、音大ならピアノが上手なんでしょ?と言われることが多いですが、実はピアノは一番の苦手。今、ピアノが苦手な学生の気持ちがすごくよくわかるので、あの時に苦戦してよかったな、とポジティブに捉えています(笑)。
大学時代、教育実習にも行きました。初めての実習では実習日誌に何を書くかもわからないまま現場に行って、「子どもたちが一生懸命頑張っている姿がかわいかったです」みたいな小学生の感想文並みの日誌を書いていましたね…。「今回感じたことは貴重な経験だけど、次はもっと深く物事を捉えるようにしましょうね」とアドバイスをもらったり。就職したのは、4年次に実習に行った幼稚園。先生方の子どもに対する眼差しが優しくてあたたかい園でした。11年間勤めたのですが、本当に楽しかった。一番の思い出なんて選べないです。ありすぎて(笑)。
入園式翌日、お母さんと離れるのが嫌で泣きながら登園してきた3歳の女の子。園にいる間ほぼ泣きっぱなし。1週間ぐらい続いていたのですが、ある日突然リュックのポケットに手を入れて「…よかったら…これどうぞ」と泣きながら持ってきてくれた。何かと思えば、袋に入っていない裸のままの梅昆布!きっと昨日のおやつに食べて「1枚はとっておいて、明日真澄先生に持っていってあげよう」って思ってくれたんだろうな。想像すると胸が熱くなった。本来であれば「おやつを持ってきちゃダメだよ」と注意すべきところですが、ルンルンで受け取りました。特別じゃないふつうの日常が豊かで面白い。それが私の大好きな幼稚園という場所です。 -
研究内容について
子どもたちの遊びが息づいている。
藤田妙子さんの子どものためのオペレッタ。
 大学の授業では保育内容総論や教育実習などを担当していますが、専門として研究しているのは、幼児のためのオペレッタ。イタリア語で「小さなオペラ」という意味の言葉です。ピアノなどの伴奏に合わせて子どもたちが歌ったり、踊ったり、演じたりする音楽劇。表現活動のひとつとして保育に取り入れられています。オペレッタに挑戦する子どもたち、面白いんですよ。たとえば、園庭で遊んでいる時にも自然に取り入れて口ずさんだりする。たとえば、砂場の道具など重いものをみんなで運ぶ時に、「よいしょよいしょ」とオペレッタの一節を歌いながら運ぶんです。こちらが手渡したオペレッタが、子どもたちの遊びの中に息づいて、いつの間にかその世界を自分たちのものにしている。子どもたちの生活の一部になっている。これって凄いことですよね。舞台で演じるだけでなく、日常に溶け込んで、子どもたちの感性、行動、好奇心を広げてくれる。私がオペレッタに魅了されている理由の一つです。
大学の授業では保育内容総論や教育実習などを担当していますが、専門として研究しているのは、幼児のためのオペレッタ。イタリア語で「小さなオペラ」という意味の言葉です。ピアノなどの伴奏に合わせて子どもたちが歌ったり、踊ったり、演じたりする音楽劇。表現活動のひとつとして保育に取り入れられています。オペレッタに挑戦する子どもたち、面白いんですよ。たとえば、園庭で遊んでいる時にも自然に取り入れて口ずさんだりする。たとえば、砂場の道具など重いものをみんなで運ぶ時に、「よいしょよいしょ」とオペレッタの一節を歌いながら運ぶんです。こちらが手渡したオペレッタが、子どもたちの遊びの中に息づいて、いつの間にかその世界を自分たちのものにしている。子どもたちの生活の一部になっている。これって凄いことですよね。舞台で演じるだけでなく、日常に溶け込んで、子どもたちの感性、行動、好奇心を広げてくれる。私がオペレッタに魅了されている理由の一つです。
オペレッタには様々な作品がありますが、私が研究しているのは藤田妙子さんの作品。大正時代の著名な童謡作曲家である弘田龍太郎さんを父に持ち、厳しい音楽教育を受けてこられた方なので、音楽・作品そのものももちろん素晴らしいのですが、藤田妙子さんの作品を演じる子どもたちの反応がイキイキしているんです。作品そのものに遊び心がある。それもそのはず。藤田妙子さんは東京・世田谷に幼稚園を開いて、自ら先生をしながら作家活動をおこなっていた方。先生として現場に立ち、園の子どもたちの遊びを間近に見ながら、その世界観をもとにオペレッタを作り上げるという方法だったんです。子どもの遊びと表現が地続きであること。それは私が保育の中でとても大切にしている感覚です。子どもたちが、物語の役や場面をまるで自分自身のもののように楽しんでいる姿に出会うたび、その思いが深まっていきます。私が目指すのは、そんな遊び心と表現の喜びが行き来するような保育です。
オペレッタも教育活動のひとつなのでねらいをもって取り組んでいます。でも、それは大人が決めた枠に子どもをあてはめることではないんです。枠にはめようとした途端、オペレッタそのものが楽しくなくなってしまう。子どもたちには、音楽を感じながら場面の雰囲気を想像したり、登場人物になりきって気持ちを味わったりしながら、感じたことを自分らしく表すことを大切にしてほしいと思っていました。子どもたちはノッてくると自分たちの劇をもっと面白くしようと、あれこれ動き出します。自分なりにアレンジしたり、演出を加えたり。大人が想像もしなかったようなことをやってみせる。子どもたちの中で自由に広がっていく何か。思いがけなく生まれてくる何か。ワクワクしますね。みなさんにもぜひその醍醐味を味わってほしいです。 -
学生のみなさんへ
保育は楽しい。子どもとの日々は面白い。
現場で感じてきた醍醐味を伝えたい。
 現場で感じてきた醍醐味を伝えたい。
現場で感じてきた醍醐味を伝えたい。
幼稚園で先生をしていた頃、集団の中で自分の居場所を探しているようだった3歳の女の子がいました。彼女がオペレッタに興味をもったんですね。年長のクラスが練習していると、自分の椅子を持ってきて、座ってじーっと見入っている。次第に「自分が年長になったら絶対にやるんだ!」と意気込むようになってきた。年中になったら「ねえねえ、来年何やるの?」なんて質問してきて楽しみで仕方ない様子。オペレッタをきっかけに、彼女の中の何かが動き出したのが手に取るように伝わってきました。彼女がずっと楽しみにしていた年長組のオペレッタ。大好きなオペレッタの世界を、友達とともに心から楽しんでいる様子がとても印象的でした。いつの間にか彼女のまわりには友達が集まり、温かなつながりが生まれていました。もちろん彼女にとっての園生活はオペレッタだけでは語りきれません。毎日の中で、泣いたり笑ったりしながら友達との関わりややりとりをたくさん重ねてきました。その積み重ねがあったからこそ、オペレッタの場面で、友達と心を通わせながら楽しんでいる姿が今でも心に残っているのです。
幼稚園で11年間がむしゃらに頑張って、自分の中にあるものをすべてを絞り出してしまったような気持ちになり、足りなかった穴みたいなものを埋めたいと思い、大学院に進学しました。視野が広がった貴重な時間になりました。そういえば、私が幼稚園を辞めて大学院に行くことになった時、ある子どもが手紙をくれたんです。「ずっと友達でいてね」と書かれていた。私は、先生と園児である前に「人と人」でありたいと思って、日々子どもたちと接していたので、それが子どもにも伝わっていたんだなぁと嬉しくなったこと、今も忘れられません。そこから御縁があり、先生になるみなさんを教える先生になりました。着任したばかりの頃は、保育・教育に携わる者としての責任や重みをきちんと伝えなければと肩に力が入りすぎていたように思います。もちろん大事なことではあるのですが、現場経験を11年も積んできたわけなので、その楽しさをみなさんにもっと伝えたい。私自身、子どもたちからたくさんの元気と勇気をもらってきました。保育は楽しい。子どもたちとの日々は面白い。私が現場で感じてきた保育の魅力を、みなさんに熱く楽しく伝えていけたらいいなと思っています。

先生と学生である前に、
人と人でありたい。
保育の魅力を
伝えることが私の役目です。
 3つのキーワード
3つのキーワード
-
01食べること

食べることが大好き。食べたことのないものを見つけたら絶対に食べたい!旅行先で見つけた不思議なものもぜんぶ食べてみたい、味わってみたい。特に現地でしか食べられないご当地ものは素通りできません。ソフトクリームが大好きで、日本各地で見つけたら必ず食べています。観光地に行くと、あちらこちらに珍しい味のソフトクリームがあるのでソフトクリームのハシゴをします。時間がないときは両手に持って交互に食べます。
-
02旅

旅をするのが好きです。現地の文化や人とのふれあいを通して、知らない世界を知ることができるからです。初めてヨーロッパに行ったのが、中学1年の時。合唱団の演奏旅行でした。3〜4週間かけてオーストリア、スイス、イタリア、チェコ、ドイツをまわり、教会や市庁舎など、さまざまな場所を訪れて歌いました。 古い街並み、教会の鐘の響き、現地の人々の温かな拍手…異国の文化や人との出会いの喜びを感じたことを覚えています。 この経験が、私に「知らない世界を知る楽しさ」を教えてくれました。今でも時間ができると、知らない世界を旅してみたくてたまらなくなります。
-
03面白いものと出会いたい

最近出会った面白いものは、友人に誘われていったコンサートで見た不思議な楽器、オンド・マルトノ。鍵盤とリボンと呼ばれるワイヤーを使って音を出す電子楽器です。調べてみたら、習える教室を発見。習ってみたい!こんな調子で、スキューバダイビング、ボルダリング、乗馬など、気になったものは一通りやるのですが、体験に行って満足する。飽き性かと思われるかもしれませんが、一度始めたことは長く続けるタイプです。だからこそなかなか始められない。一度始めたら一生物の覚悟が伴うので!
こんなこと学べます、
ゼミ生たちの卒業論文
保育における劇活動の課題点の検討ー卒園生へのインタビューを通してー/幼児の思いやりを育むための援助の在り方に関する研究ー幼稚園における事例をもとにー/実習前後の保育者効力感の変化に関する一考察ー保育者養成校3・4年生のアンケート結果からー/幼保小接続の在り方についての検討ー文部科学省「幼保小の架け橋プログラム事業」採択自治体を例にー/絵本「ぐりとぐら」における子どもの「喜び」や「楽しみ」に繋がる要素の検討/アンパンマンが子どもの正義感に与える影響-やなせたかしの正義論に着目してー/保育における繊細な子どもへの向き合い方の検討ー保育者へのインタビューを通してー/大学生の主観的幸福度と人間関係の主観的満足度の比較と検討〜アンケート調査をもとに〜/ドキュメンテーション記録が与える効果に関する一考察ー保育観察と保育者のインタビューを通してー
著書・論文
-
幼児教育におけるオペレッタの普及とその歴史的背景―保育雑誌におけるオペレッタ記事に着目して―
[論文]単著/日本保育文化学会 保育文化研究(15)/2022
本稿は、昭和20年代末から創刊された保育雑誌の記事を分析し、幼児教育におけるオペレッタの普及経緯と歴史的背景を考察した。 領域別指導から子ども主体の創作活動への変遷を明らかにし、教育現場での意義を再評価している。
-
幼稚園・認定こども園におけるカリキュラム・マネジメントの実践上の課題―幼稚園教諭と保育教諭に対するインタビューを通して―
[論文]単著/東京未来大学研究紀要(18)/2024
幼稚園・認定こども園におけるカリキュラム・マネジメントの課題を、保育者へのインタビューを通じて分析した。保育の質の担保と業務の効率化、学び続ける保育者としての取り組み、ミドルリーダー育成と保育者アイデンティティの再構築という3つの視点を提示し、園運営と保育者の資質向上の関係性を考察している。
-
保育内容総論-ICTを活用した計画と教材研究-
[著書]共著/建帛社/2024
保育実践でのICT機器活用の可能性を考えた「保育内容総論」のテキスト。理論編では総論の基本的内容を押さえつつ、実践編では園で過ごす1日の流れにそってICT機器を活用した実践事例を多数掲載し、解説している。