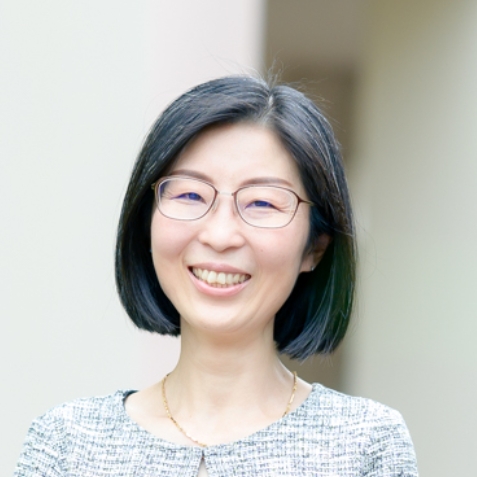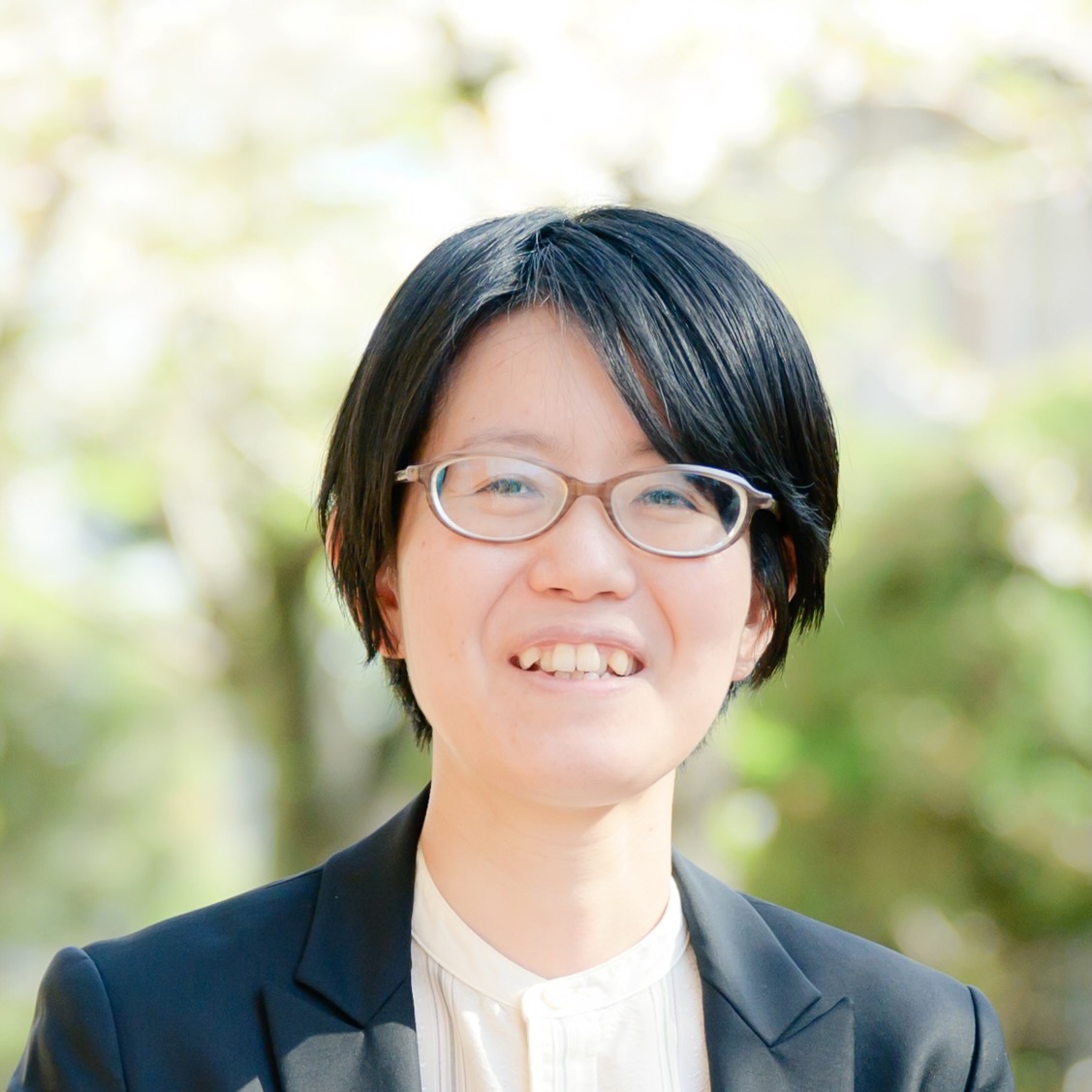PROFILE
鈴木 公啓SUZUKI TOMOHIRO
詳細をみる
東洋大学大学院社会学研究科博士後期課程修了。東洋大学や明治学院大学等の非常勤講師、東洋大学HIRC21のPD研究員を経て現職。
専門:
パーソナリティ心理学、社会心理学
主な担当科目:
感情・人格心理学A、心理学応用研究法実習B、子ども心理学特別講義など
-
心理学に興味をもったきっかけ
心理学ってなんだろう。どんな学問なんだろう。
わからないから、興味をもった。
 本が好きな子どもでした。地域の公民館のようなところに本の部屋があって、片っ端から読んでいました。自分が体験できないことも、本の世界なら体験できる。地元・岩手の作家である宮沢賢治の作品も、よく読んでいましたね。心理学に興味を持ったきっかけも本でした。実は高校2年の終わり頃までは医者になろうと思っていたんです。たまたま読んだ本の登場人物に、心理学者が出てきたんですよ。ストーリーとはまったく関係なかったのですが、なんとなく気になった。実家に、岩原信九郎先生の『教育と心理のための推計学』という著書があったけど、読んでもなんだか意味がわからない。ますます謎が深まっていきました。この、心理学ってよくわからない学問だということが,興味をもたせました。生物学や教育学は何を学ぶのかなんとなくイメージが沸きますよね。でも心理学は見当もつかなかった。また、当時は進学先も限られていました。国立大の心理学科はお茶の水女子大学と広島大学の2つだけ。女子大は入れないので、じゃあ広島大学だと。理系でも受験ができましたし。
本が好きな子どもでした。地域の公民館のようなところに本の部屋があって、片っ端から読んでいました。自分が体験できないことも、本の世界なら体験できる。地元・岩手の作家である宮沢賢治の作品も、よく読んでいましたね。心理学に興味を持ったきっかけも本でした。実は高校2年の終わり頃までは医者になろうと思っていたんです。たまたま読んだ本の登場人物に、心理学者が出てきたんですよ。ストーリーとはまったく関係なかったのですが、なんとなく気になった。実家に、岩原信九郎先生の『教育と心理のための推計学』という著書があったけど、読んでもなんだか意味がわからない。ますます謎が深まっていきました。この、心理学ってよくわからない学問だということが,興味をもたせました。生物学や教育学は何を学ぶのかなんとなくイメージが沸きますよね。でも心理学は見当もつかなかった。また、当時は進学先も限られていました。国立大の心理学科はお茶の水女子大学と広島大学の2つだけ。女子大は入れないので、じゃあ広島大学だと。理系でも受験ができましたし。
大学時代は、勉強よりもアルバイトに夢中でした。そのアルバイトは、遺構発掘のアルバイト。スコップなど様々な道具で掘って、ネコ(一輪車)で土を運ぶ。捨ててきて、また運ぶ。トップカー(小さなトラックのようなもの)で土を運んだりもしました。基本的には肉体労働なんですが、私は図面をとらせてもらってもいました。測量して紙に落とし込むのです。そうそう、土の層が見えてくるというのが面白いんですよ。土の層は年代によって違うのですが、はじめはわからない。しかし、経験を積むとそれがすぐにわかるようになってくる。見るだけでなく,道具越しでも土が変わった瞬間がわかる。マニアックですよね(笑)。これまで見えなかったものが見えるようになる、というのは面白い体験でした。心理学の研究に火がついたのはちょっと遅くて大学院生の時。ふと思い立って心理学を基礎から学びなおしたんです。博士課程ではダイエットについて研究しました。ところが、長い研究人生を考えるとダイエットはテーマとして狭すぎるんですよね。そこから模索しながらテーマを広げていき、装いや外見について研究するようになりました。 -
研究内容について
日本には数える程しかいない、“装い”の心理学の研究者。

 「見た目ばかり気にしてないで、勉強しなさい」と言われたことはありませんか?親が子どもに言うシーン、いろいろなところで見聞きしますよね。見た目のことは、勉強やスポーツよりも重要ではない、というなんとなくの認識が共有されている。心理学においても、装いや外見というテーマは、長い間“くだらない”テーマだといわれてきたんです。今はその風潮も少し変わってきたように思いますが、僕が博士課程の頃は、まだその風潮が強かった。これは心理学だけでなく、哲学など他の学問についてもそうだったようです。だからこのテーマで学位を取るのは難しいと言われたこともありました。装い・外見に関する心理学の研究者がほとんどいないから、先行研究もかなり限られている。だから僕の研究は、未開の地をブルドーザーで切り拓いていくような道のりでした。たとえば、日本でタトゥーや美容整形や脱毛などをテーマとした心理学の研究を検索すると、でてくる論文や本や記事はその多くが僕のものだと思います。「子どものおしゃれ」を検索しても同じでしょう。それくらい研究者がいない。以前は,近い研究テーマの人などに声をかけて、研究会を開催したりしていました。それぞれの研究を発表したり、心理学以外の専門家をお招きして話をしてもらったりしたこともありました。人とつながって、協力しあって、一歩ずつ研究を進めてきて、今があります。
「見た目ばかり気にしてないで、勉強しなさい」と言われたことはありませんか?親が子どもに言うシーン、いろいろなところで見聞きしますよね。見た目のことは、勉強やスポーツよりも重要ではない、というなんとなくの認識が共有されている。心理学においても、装いや外見というテーマは、長い間“くだらない”テーマだといわれてきたんです。今はその風潮も少し変わってきたように思いますが、僕が博士課程の頃は、まだその風潮が強かった。これは心理学だけでなく、哲学など他の学問についてもそうだったようです。だからこのテーマで学位を取るのは難しいと言われたこともありました。装い・外見に関する心理学の研究者がほとんどいないから、先行研究もかなり限られている。だから僕の研究は、未開の地をブルドーザーで切り拓いていくような道のりでした。たとえば、日本でタトゥーや美容整形や脱毛などをテーマとした心理学の研究を検索すると、でてくる論文や本や記事はその多くが僕のものだと思います。「子どものおしゃれ」を検索しても同じでしょう。それくらい研究者がいない。以前は,近い研究テーマの人などに声をかけて、研究会を開催したりしていました。それぞれの研究を発表したり、心理学以外の専門家をお招きして話をしてもらったりしたこともありました。人とつながって、協力しあって、一歩ずつ研究を進めてきて、今があります。
メディアからの取材もたまにくるのですが、最近は子どもの化粧について聞かれることが多いです。子どもの美容整形についても聞かれることがあります。日本の場合は法律で規制されていないので、親が同意すれば子どもが何歳であってもできてしまう。いろいろいろな意見がありますが、僕は基本的に「本人に考えさせること」が大事だと思っています。子どもって無意識のうちに親の意見を取り込むんですね。だからどこまでが本当の自分の意見なのか、線引きもできないし、誰にもわからない。最初はやりたいと言っていたものの、後になってやっぱり違っていた、となる可能性も否定できない。機能的な問題がない限りは、本人が自律・自立してしっかりと考えられるようになるまで、待ったほうがいいというのが僕の個人的な考えです。本人が「自分で考えて決める」という機会を奪わないことが大事だと思います。外見を考えることは、内面を考えるきっかけにもなる。本人がポジティブに活用できるといいなと思います。 -
学生のみなさんに伝えたいこと
装い・外見は、社会において
自分を乗りこなすためのツールでもある。
 装い・外見というものは、“社会との接点”と捉えることもできます。たとえば、どんな服装、どんな髪型にするか考えることは、「自分をどのように社会に適合させていくのか」を考えることでもある。その上で、せめぎ合いもありますよね。物事にはルールがありますから。校則を守ってはいるけれども、ちょっとだけ自分の好きなようにしたいとかあるわけじゃないですか。何をするにしても、社会がどうなのか、自分はどうなのかを認識して、その上で決める。社会において自分をどう乗りこなすのか考える。“装い”というものは一つのツールなんですね。“装い”をきっかけに、社会を知り、自分を知ることができる。
装い・外見というものは、“社会との接点”と捉えることもできます。たとえば、どんな服装、どんな髪型にするか考えることは、「自分をどのように社会に適合させていくのか」を考えることでもある。その上で、せめぎ合いもありますよね。物事にはルールがありますから。校則を守ってはいるけれども、ちょっとだけ自分の好きなようにしたいとかあるわけじゃないですか。何をするにしても、社会がどうなのか、自分はどうなのかを認識して、その上で決める。社会において自分をどう乗りこなすのか考える。“装い”というものは一つのツールなんですね。“装い”をきっかけに、社会を知り、自分を知ることができる。
先ほど、外見というテーマはくだらないと認識されている話をしましたが、実際には外見が自分や周りに与える影響って大きいですよね。外見のことは二の次、三の次でいい、と言われる割に、現実では外見で評価されることも多い。それなのに「人は外見じゃないよね」という。そう、外見のことは建前と本音がこんがらがって、ねじれているんです。外見は外見として重要だし、装うことは楽しいことでもある。社会適応という意味では必要なことでもある。外見というものを私たちがもう少し素直に受け止めることができるようになったら、もっと生きやすい世の中になるのではないかと思っています。
学生のみなさんに伝えたいことは、いろいろなことに興味を持ちましょうということです。外界に意識を向ける。外に目を向けることで、いろいろな疑問も湧いてくるはず。本を読むこともしかり。先ほども触れましたが、自分で体験できないことを本の中では体験できる。こんなことをやらかしたらこんな風に大変なことになるぞ!というのも、実際にやるとリスクを伴いますが、本だと無傷で学べますから。いろいろな知識、いろいろな経験を得る。それはきっと皆さんの人生において大きな糧になってくれるはずです。

いろんなものに興味を持とう。
外の世界に意識を向けよう。
意識を向けると、世界が広がる。
自分の人生も広がります。
 3つのキーワード
3つのキーワード
-
01ループタイ

ネクタイ締めるのが好きじゃないんです。何かしないといけないのであれば、ループタイでいいかと、軽いきっかけでつけ始めました。男性用で気に入るのはなかなか売っていないので、自作しています。女性用のブローチの後ろの金具を外して、ループタイのパーツをつけたり、レジンで細かい石を固めたりして作っています。だから、世界に一つ。一点モノです。おしゃれのこだわりかと言われるとちょっと違うのですが、単に作るのが楽しくてやっています。
-
02料理

和食は基本的なものは一通り作ることができます。天ぷらから煮魚まで何でも作る。休日は朝から市場に魚を買いにいくことから始まります。お刺身にして、残りを昆布締めにしたり。あん肝やカレイの唐揚げなんかも作ります。ちなみに今日の朝ごはんはタゼリの炊き込みご飯でした。包丁も自分で研ぎます。東京には魚の市場が3か所あるんですが、足立区にある足立市場はマグロの競り以外は一般の人も入って買うことができます。一度に何種類か買って、一つひとつ丁寧に料理して、数日にわたり食卓に並べて、そして食べます。写真はサバの真子の煮付けです。
-
03家庭菜園

基本的には「食べ物に関するもの」を育てています。たとえば大葉や茗荷、パセリなど。薬味系は新鮮なものを使いたいので。ほかにも珍しい果物を育てたりしています。「おっ、芽が出てきたぞ」「春になって葉っぱがまた生えてきたぞ」と、育つ様を見る楽しさもある。日々変化していくことに面白さを感じています。
こんなこと学べます、
ゼミ生たちの卒業論文
出会い方による飼い主とペットの類似性の違い/視線から嘘を読みとることはできるのか/マスクの色が顔記憶に与える影響/結婚指輪の有無が外見的魅力と内面的魅力に及ぼす影響/演奏する音の高さが奏者の印象に及ぼす影響/美容整形経験のカミングアウトによる対人関係の変化ー場面想定による検討ー/鏡を見ることが自己受容感に及ぼす影響-アングルによる違いの検討-/身体の自己評価と肌見せ系ファッションとの関連/親密な友人の惚気話を聞いた際に生起する感情/体型満足度が試着時の賞賛後の購買行動に及ぼす影響
著書・論文
-
子どものおしゃれにどう向き合う?―装いの心理学ー
[著書]単著/筑摩書房/2025
子どものおしゃれの実態とその背景について、データをもとにまとめたもの。親の関わり方などにも触れている。
-
装いの心理学ー整え飾るこころと行動ー
[著書]編著/北大路書房/2020
化粧から美容整形から姿勢や言葉など、多様な装いの内容について、基本的なことをまとめたもの。装いの心理学の入門書。
-
<よそおい>の心理学-サバイブ技法としての身体装飾-
[著書]共編著/北大路書房/2023
装いの心理的機能について、多側面からまとめたもの。「装いの心理学ー整え飾るこころと行動ー」の姉妹本。こちらは専門的な内容。