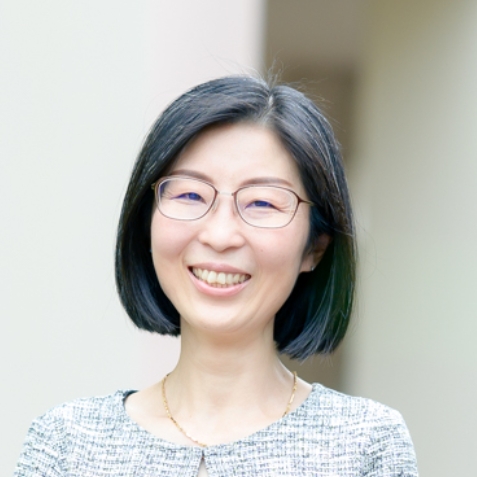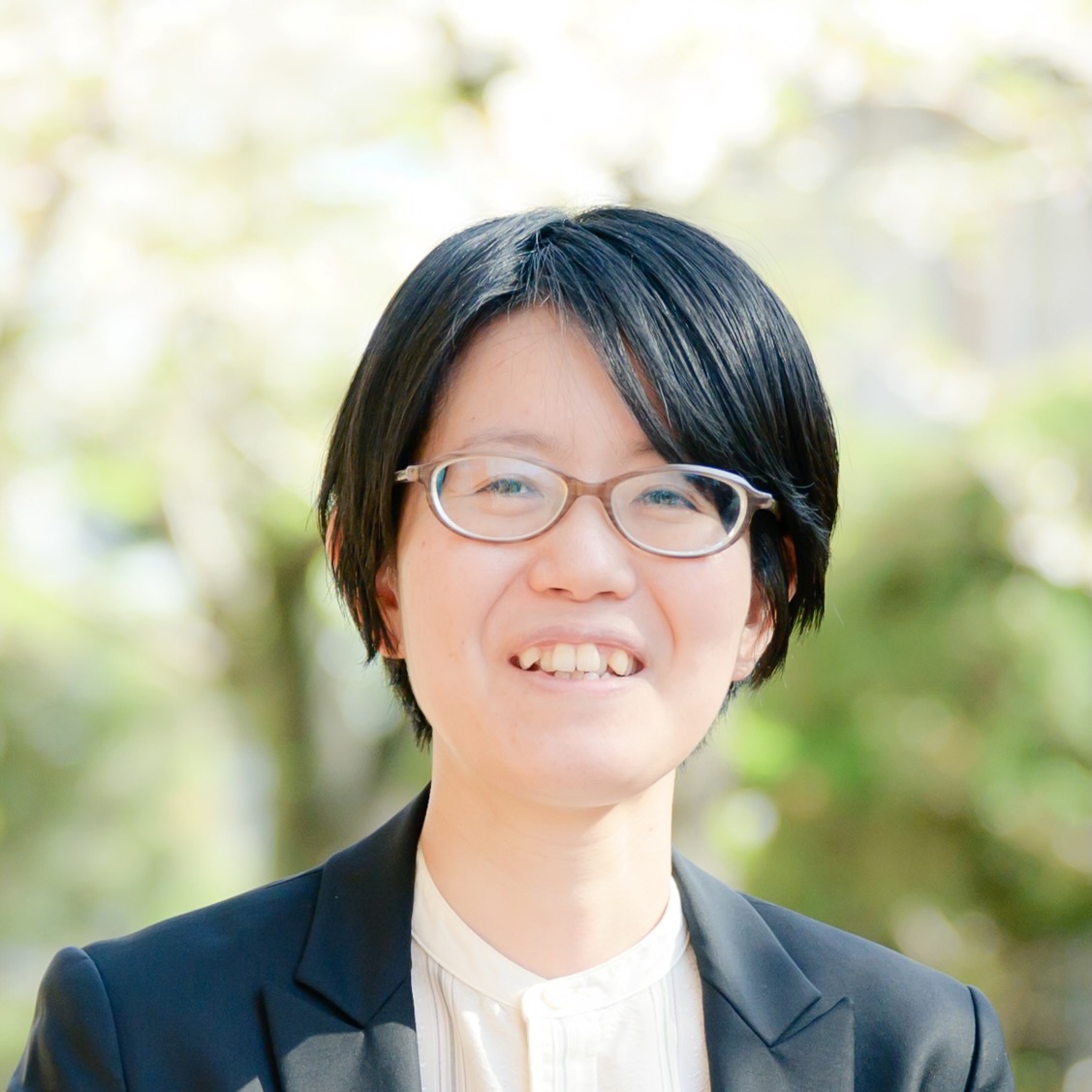PROFILE
埴田 健司HANITA KENJI
詳細をみる
一橋大学社会学部卒業。
一橋大学大学院社会学研究科修士課程、同博士後期課程修了。博士(社会学)。
追手門学院大学心理学部特任助教、東京未来大学モチベーション行動科学部講師を経て、現在は同大学同学部准教授。専門は社会心理学。
専門:
社会心理学
主な担当科目:
社会・集団・家族心理学A(社会)、社会・集団・家族心理学B(集団)、心理学統計法Ⅰなど
-
心理学に興味をもったきっかけ
“社会”ってなんだろう?
よくわからないから気になった。
 高校生の頃、“社会”ってなんだろうなといった漠然とした疑問がありました。僕たちはみんな“社会”の中で生きているけれど、“社会”って一体どうやって成り立っているんだろうなと。当時は偏差値教育の時代だったこともあり、自分の偏差値で入れそうな大学レベルから、学部を選ぶのがわりと一般的だったんですね。法学部も経済学部も何を学ぶかだいたい想像できる。え、社会学部?何それ?何を学ぶのかよくわからない感じが面白そうだな、と思った。そんなふわっとした気持ちで社会学部へ。心理学に興味をもった理由は、たまたま一般教養の心理学の授業を受けて、面白い!と興味を惹かれたから。モチベーション行動科学部の学生たちも、「何を学びたいか今ははっきりわからないけど、学んでみてから決めよう」という人が多いと思います。そう、僕も最初ははっきりした目的があったわけではなかったんです。
高校生の頃、“社会”ってなんだろうなといった漠然とした疑問がありました。僕たちはみんな“社会”の中で生きているけれど、“社会”って一体どうやって成り立っているんだろうなと。当時は偏差値教育の時代だったこともあり、自分の偏差値で入れそうな大学レベルから、学部を選ぶのがわりと一般的だったんですね。法学部も経済学部も何を学ぶかだいたい想像できる。え、社会学部?何それ?何を学ぶのかよくわからない感じが面白そうだな、と思った。そんなふわっとした気持ちで社会学部へ。心理学に興味をもった理由は、たまたま一般教養の心理学の授業を受けて、面白い!と興味を惹かれたから。モチベーション行動科学部の学生たちも、「何を学びたいか今ははっきりわからないけど、学んでみてから決めよう」という人が多いと思います。そう、僕も最初ははっきりした目的があったわけではなかったんです。
今は学びたいものがないけれど、学んでいく中で、これ面白い!と思えるものに出会うことができる。僕も幸い出会えた。3年次には念願の社会心理学のゼミに。最初に興味を持って学んでいたのは消費行動。卒論に選んだのは、お酒の広告効果の研究でした。CMでタレントがビールをグビグビ飲んでいますよね。実際に飲んでいる姿というものは、広告を見る側の人にとって飲んでみようと思われる効果があるのか?どのような影響を及ぼすのか?僕の場合はCMではなく印刷広告についてでしたが、タバコの広告効果の先行研究があったので、そうしたものを参考にしながら書き上げました。
大学院では偏見、ステレオタイプ、集団に対するイメージについて研究するようになりました。このテーマを深く考えるようになったきっかけがあります。大学院1年の冬にアメリカの学会に行った時のことです。はじめての海外学会で、ドキドキしていたこともありますが、街中で黒人とすれ違った時に、怖いと感じて距離を置いてしまったんです。怖いと感じてしまった自分にショックを受けた。人種差別の歴史、欧米の社会の中で黒人が虐げられてきたということ、それでも以前に比べれば人種差別がなくなってきていることは知識として持っていた。その一方で、今でも「黒人には犯罪者が多い」という偏見を持つ人がいる、ということも知っていた。人種差別がいけないことはわかっているのに、なぜそんな風に偏見を持つの?と思っていた。そう、自分には偏見なんかないと思っていたんです。でも実際にアメリカに行って、黒人の人とすれ違った時に距離を置いてしまった。これはなんなのだろうかと。そうか、偏見とは自分で気付けるものではなく、“非意識”として自分の中にあるものなんだ。こうして僕は“意識できない範囲の中で、その人がどう思っているのか?”ということを深掘りして研究していくようになります。 -
研究内容について
偏見なんか持っていないつもり。
でも、“非意識”で持っている?
 偏見やステレオタイプって、僕たちの身近によくあるものです。ちなみに、僕は中学までは野球部だったのですが、バンドをやっていたこともあり、高校では吹奏楽部に入ったんです。その時にピアノを弾ける男子が何人もいることにカルチャーショックを受けた。「え、男子なのにピアノ弾けるの?」と。これ、偏見でありステレオタイプですね。ちなみにステレオタイプとは簡単に言うと、集団に関して多くの人に浸透している固定観念や思い込みのこと。言い訳させてもらうと、僕は群馬の片田舎(村!)の中学から都市部の高校に進学したのですが、田舎ではピアノを習っているのは女子ばかりだった。だから、「音楽=女子」というイメージが強かったんですね。今思えば、こうした実体験が今の研究につながっているような気がします。
偏見やステレオタイプって、僕たちの身近によくあるものです。ちなみに、僕は中学までは野球部だったのですが、バンドをやっていたこともあり、高校では吹奏楽部に入ったんです。その時にピアノを弾ける男子が何人もいることにカルチャーショックを受けた。「え、男子なのにピアノ弾けるの?」と。これ、偏見でありステレオタイプですね。ちなみにステレオタイプとは簡単に言うと、集団に関して多くの人に浸透している固定観念や思い込みのこと。言い訳させてもらうと、僕は群馬の片田舎(村!)の中学から都市部の高校に進学したのですが、田舎ではピアノを習っているのは女子ばかりだった。だから、「音楽=女子」というイメージが強かったんですね。今思えば、こうした実体験が今の研究につながっているような気がします。
いま僕はこうして話していますが、人間は何を話そうかと頭の中で考えながら話していますよね。でも、その背後に、意識しないレベルでもっといろんなことを考えているんですよ。人間が自分で意識できている部分というのは氷山の一角なんです。僕の研究では、このような自分では意識できない“非意識”を扱うので、研究では一般的なアンケートとは異なる手法を使います。「あなたは黒人についてどう思っていますか?」と質問しても、意識できる範囲の答えしか出てこない。なので、意識できない部分を抽出する方法でなければいけません。たとえば、ジェンダーで言えば、「男は仕事、女は家庭」みたいな考え方がありますよね。現在の世論調査の結果では、6割弱の人がこうした考え方には反対と答えています。でも、非意識をあぶりだす調査をおこなうと結果が違うんです。たとえば、男性や女性の名前、仕事や家庭に関係する言葉をたくさん縦一列に並べておいて、男性の名前と仕事関係の言葉を左側に、女性の名前と家庭関係の言葉を右側に分けてもらう方法。これで分けやすいっていうことは、「男は仕事、女は家庭」と非意識的に考えているっていうこと。授業でも学生にやってもらうんですけど、みんな驚きますよ。「自分ではそう思ってなかったけど、私も“男は仕事で女は家庭”って思ってたんだ…」とショックを受けたりしている。僕も子どもがいるので、保育園にお迎えに行くのですが、いまだにお母さんが多い様子を見て考えます。世の中では男女平等だと言われていても、実際はそうじゃないところもある。背後に意識できない“非意識”が根強く横たわっているんだなと。
僕は非意識の研究をおこなっているので、それが一部意識化されていくことでギャップを解消することができればと考えています。今の社会が抱えている課題にはどのような心理的なプロセスがあるのか。現状がわかれば、改善するための仮説も導くことができる。東日本大震災が起きて原発事故が発生した。風評被害なんてないと言われているが、実際はどうなのか。消費者側の立場に立った時に、どういった要因がネガティブなイメージに繋がっているのか。それを改善するためにはどうすればいいか。性的マイノリティもそう。LGBTQ、多様性は大切だと言われているけど、実際はどうなのか。“非意識”を土台にした僕の研究は社会のリアリティを見つめることでもあります。 -
学生のみなさんに伝えたいこと
偏見をなくすことは難しい。
そんな中で、よりよく生きていくためには?
 偏見というものと、どううまく付き合っていくのか、という風に考えた方がいいのではないかと思っています。なくすことは難しいけれど、多少なりとも弱める方法はあると思うんです。たとえば、女性の管理職が少ないという問題。男性が上司で、女性はサポート役。でも、有名な女性のリーダーがメディアに露出するようになったらどうなるだろうか。活躍する女性を目の当たりにすることで、“女性”と“仕事”の概念が強く結びつくようになってくる。そうすると非意識の部分が徐々に変わってくると思うんです。研究をするなかで、自分なりによくわかったことは、意識できる部分はごく一部でしかない、ということです。そう、意識って当てにならないぞ、ということでもあります。バイアスだらけ。歪みだらけ。さっき、学生時代の話もしましたが、その認識だって、歪んでいるかもしれない(笑)歪んでいるからうまく生活できている側面もある。こころは現実を正確に映す鏡ではないんですよね。だから心理学って面白いんですけどね。
偏見というものと、どううまく付き合っていくのか、という風に考えた方がいいのではないかと思っています。なくすことは難しいけれど、多少なりとも弱める方法はあると思うんです。たとえば、女性の管理職が少ないという問題。男性が上司で、女性はサポート役。でも、有名な女性のリーダーがメディアに露出するようになったらどうなるだろうか。活躍する女性を目の当たりにすることで、“女性”と“仕事”の概念が強く結びつくようになってくる。そうすると非意識の部分が徐々に変わってくると思うんです。研究をするなかで、自分なりによくわかったことは、意識できる部分はごく一部でしかない、ということです。そう、意識って当てにならないぞ、ということでもあります。バイアスだらけ。歪みだらけ。さっき、学生時代の話もしましたが、その認識だって、歪んでいるかもしれない(笑)歪んでいるからうまく生活できている側面もある。こころは現実を正確に映す鏡ではないんですよね。だから心理学って面白いんですけどね。
偏見を持たれることで傷つく人がいます。不利益を被る人がいます。実際ちゃんと調べてみるとそうじゃないのに。つまり、火のないところに煙が立ってしまう。そうした現実がある中で、私たちが社会の中でよりよく生きるためにはどうすればいいんだろう。そんなことを考えながら学生たちに指導しています。大学で授業を持つものとして、学生のみなさんにはしっかり学んでほしいし、単位も取って欲しい。みんなも義務感に駆られていると思います。でも、それだけではなく、自分の理想とか、こんなことをしてみたいという願望に向かって行動することも忘れないでほしい。やらされるのではなく、自分の意思で何かに取り組んだ経験は人生の大きな糧になる。みんなの4年間をしっかり応援したいと思います。

“やらなきゃいけない”だと
受け身になりがち。
やりたいことを大事にしよう。
経験の積み重ねが糧となります。
 3つのキーワード
3つのキーワード
-
01子育て

ご飯を作る。送り迎えもする。掃除も洗濯もする。家事の6割は僕がやっているはず!余談ですが、夫婦間で家事分担割合の自己評価アンケートをとると、ほとんどの場合は夫婦の合算数字が10割超えるんですよ。自分の貢献度を過大に見積もる傾向にある。うちの妻も「7割やってます」と言いそうな気がします(笑)
-
02料理

料理はよくします。生米からパエリアを作ったり、鶏ガラを半日煮込んで水炊き鍋をやってみたり、クリスマスの時には丸鶏を焼いたり。作って楽しいし、食べて美味しい。家族が喜んでくれることが一番のモチベーションになります。
-
03地図

地図を眺めながら旅のプランニングをすることが好きです。交通手段や食事処、プチ観光など旅程を空想する。たとえば次の学会が仙台になったとします。まず、はやぶさに乗って行く。何度か行ったことがあるあそこのお店にもう1回行きたいな。翌日の昼はここで牛タン食べようかな、など。家族旅行の時も予定を詰め込みすぎてしまうので、最近は反省して 、ゆったり過ごすことを覚えました。
こんなこと学べます、
ゼミ生たちの卒業論文
男女によって性的マイノリティに対する態度とカミングアウト受容度に差はあるか?―当事者から向けられる性的意図の推測に着目して―/オタクによるオタクステレオタイプとメタステレオタイプ―両者の間に生じるズレに影響する要因の検討―/身に着ける色が人物の印象に及ぼす影響/験担ぎによって行動は変わるか?―「カツ」の摂食が「勝力」に及ぼす影響―/顔写真で性格は読めるか?―外見から推測される性格特性の精度―/仲間はずれにされると食べ過ぎる―排斥状況下における高カロリー食品摂食の自己制御―/うまく自己制御するには?―非意識的目標及び心理社会的資源における自己制御―/「ひとり」はさみしい?―充実した「ひとり時間」をもたらす要因の検討―/自己高揚的・自己卑下的自己呈示が良性・悪性妬みに及ぼす影響/同担意識と推し活効果の関連―自己意識的感情の媒介に着目して―
著書・論文
-
A model for predicting attitudes toward foodstuffs produced in radioactively contaminated areas: An examination based on the fundamental motive framework
[論文]単著/Japanese Journal of Motivational Studies (モチベーション研究)/2025
原発事故で風評被害を受けた福島県産農作物に関して,感染症回避動機が「放射線・原発不安」を喚起することで購買意図を抑制する一方で,親和動機が「被災地支援」を導くことで購買意図を促進するという影響プロセスが確認された。
-
ピンク・青の衣服がジェンダーに関連する自己認知と他者認知に及ぼす効果
[論文]共著/東京未来大学研究紀要/2020
青かピンクの服を着てもらって実験を行ったところ,青よりもピンクの服を着用したときのほうが自分を女らしいと捉えていた。一方,他者に対しては男らしいと捉えており,着用した服の影響が自分と他者では逆になっていた。
-
伝統的・非伝統的女性の事例想起が潜在的性役割観に及ぼす影響
[論文]共著/認知科学/2013
「男は仕事,女は家庭」という伝統的な性役割観にあてはまらない女性(キャリア女性)を意識的に想起することによって,非意識的に持たれている性役割観が平等的な方向に変容することが実験により示された。
-
リベラルアーツとしての社会心理学
[著書]共著/八千代出版/2025
心理学を専門とする学生にもそうでない学生にもわかりやすく役に立ち,リベラルアーツとして社会心理学を学べることをコンセプトとした学術書。社会心理学の基礎的・応用的な内容を含み,メディアと社会心理の関係も述べられている。